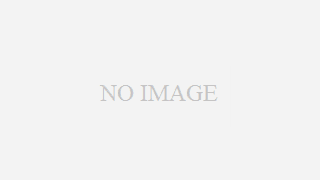 合唱組織論
合唱組織論 平成21年度群馬県合唱連盟定例総会議決に関する考察(その3)
こういうふうに、群馬県合唱連盟を批判することばかり書いていますと、このTetsuっていう輩は、かなり粘着で、合唱連盟のことが嫌いなのだと思われそうですが、 実は、これほどまでに群馬県合唱連盟のことを気に掛けている人間はいないのではないかと、...
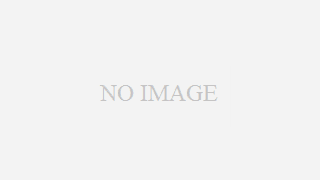 合唱組織論
合唱組織論 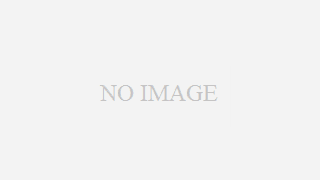 合唱組織論
合唱組織論 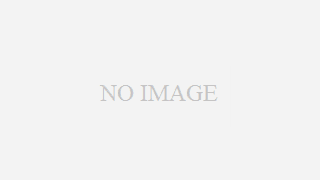 合唱組織論
合唱組織論 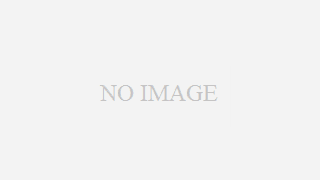 合唱組織論
合唱組織論 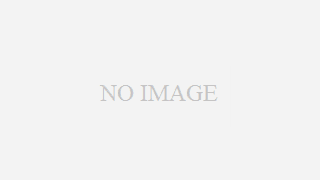 合唱組織論
合唱組織論 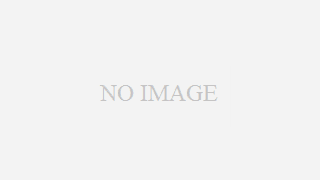 合唱組織論
合唱組織論 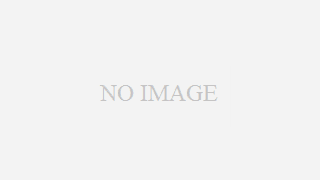 合唱組織論
合唱組織論 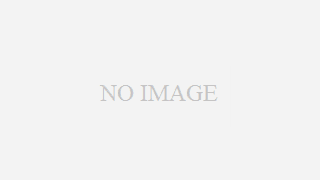 ニュース
ニュース 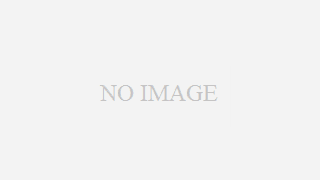 合唱組織論
合唱組織論 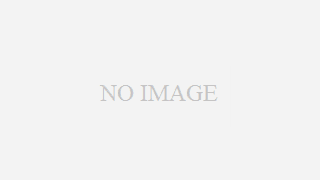 合唱組織論
合唱組織論