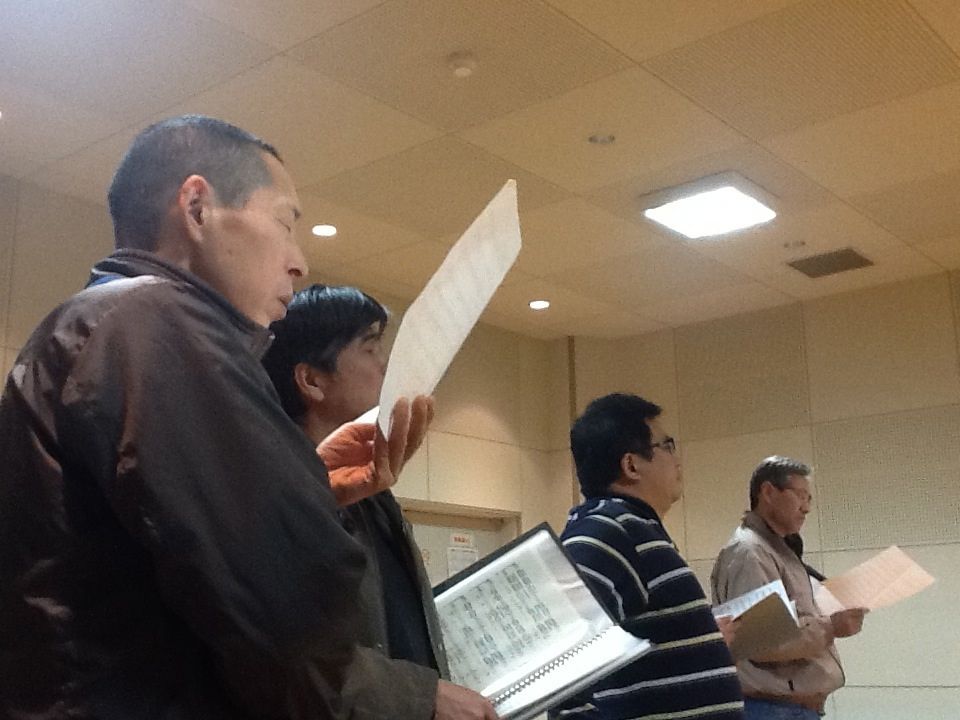 日記・コラム・つぶやき
日記・コラム・つぶやき 2012年3月17日(土)通常練習
ストイックな音取り練習が続く。今週も日本民謡集の音取りである。音取りの早い人にとっては、退屈な時間かも知れない。しかし、私のようなノロマな部類にとっては大切な時間である。ただ、それは音取りという極小的な一断面での話。そんな時間の中にも、今後...
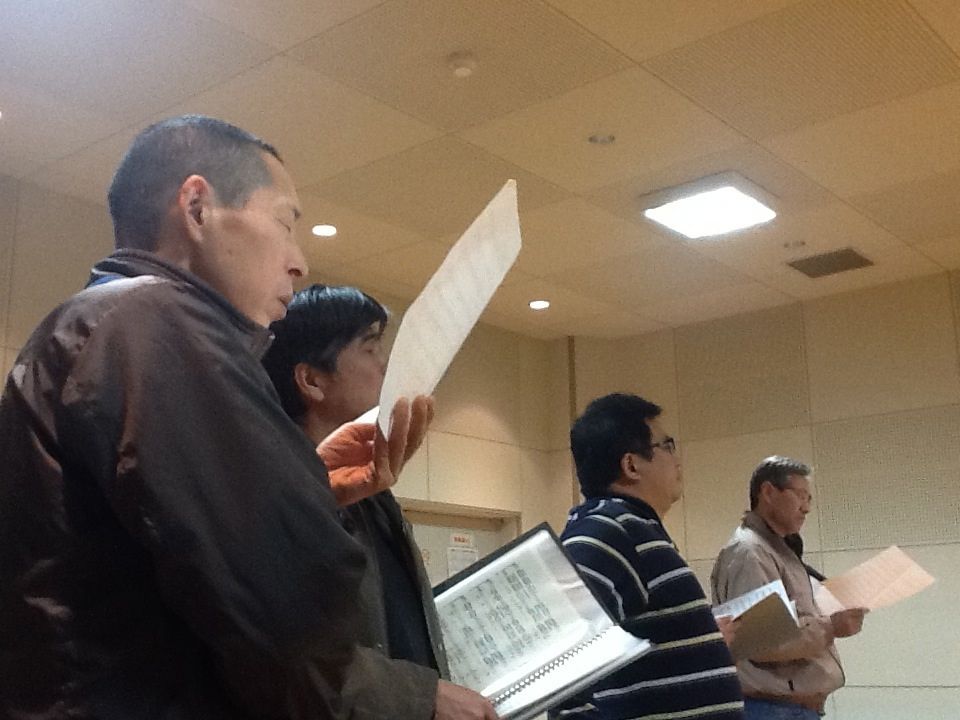 日記・コラム・つぶやき
日記・コラム・つぶやき  新入団万歳!
新入団万歳!  練習日誌
練習日誌  練習日誌
練習日誌